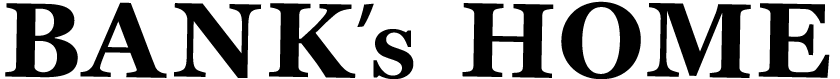賃貸併用住宅は、住宅と賃貸物件を同時に取得できる魅力的な物件。なるべく建築費用を抑えたいところですが、建築会社によっても価格は違ってきます。
今回は、多くの人が悩まれる大手ハウスメーカーと地元工務店での賃貸併用住宅の建築価格を比較し、それぞれのメリットデメリットをご紹介します。
※このブログでのハウスメーカーは「全国でエリア展開している住宅メーカー」、工務店は「地域に根付いた住宅メーカー」とさせていただきます。
目次
賃貸併用住宅の建築費は?実例を紹介

弊社の賃貸併用住宅バンクスホームを例に、建築費を紹介いたします。
間取りは3LDK+2Sが2世帯ある縦割り型の賃貸併用住宅です。
敷地は約50坪、延べ床面積は160㎡ほどの住宅です。
こちらの物件の建築費は以下の通りです。
| 本体工事費 | 3740万円(税込) |
| 付帯工事費 | 770万円(税込) |
| 諸費用 | 218万円(税込) |
| 合計 | 4728万円(税込) |
※こちらの物件は2021年に完成しましたが、その当時より建築費が高騰しているため現在の価格に修正しております。
令和3年度の統計を見ると、木造の坪単価の全国平均は57万円~60万円でした。
つまり、50坪程度の住宅だと3000万円程度ということになります。
弊社のバンクスホームも平均と変わらない価格帯でしたが、
昨今の建築資材の値上がりによって上記のような価格となっております。
(※今後も状況次第では建築費が変更になる可能性もございます。)
多くの建築会社でも値上がりの傾向はありますので、
検討している建築会社に問い合わせるのが良いでしょう。
<参考>国土交通省 令和3年度 建築着工統計調査 用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額
賃貸併用住宅の価格を比較
建築会社ごとに値段は異なります。とくに大手ハウスメーカーと工務店では、建築価格に800万円以上の違いが出ます。
その理由は、坪単価に差があるからです。
工務店の坪単価が約50万円なのに対し、ハウスメーカーは約70万、さらに大手ハウスメーカーだと80万以上の価格帯になります。
延床面積40坪の賃貸併用住宅を建築する費用を計算すると、
工務店の場合⇒50万円×40坪=2000万円
ハウスメーカーの場合⇒70万円×40坪=2800万円
となります。
どこに建築を依頼するかで建築費用に大きな差が生まれるのです。
ハウスメーカーと工務店で価格が違う理由
なぜ、ハウスメーカーと工務店では価格の違いがあるのでしょうか?
その答えは、ハウスメーカーには多くの経費がかかっているからです。
全国で事業を行うハウスメーカーでは、事業拡大するための広告宣伝費や人件費が建築費用に含まれています。
また、ハウスメーカーと契約しても実際に工事するのは下請け業者です。下請け業者も10~15%の利益を取る必要があるので、その分費用を上乗せする必要があります。
このようにハウスメーカーは会社維持のために多額の費用が必要なため、建築費用の5割が粗利だと言われています。
一方で工務店は広告費や人件費が少ないだけでなく、工事も自社で行う場合が多く経費が少なく済むため、工事費用を抑えられるのです。
ハウスメーカーで建てるメリットとデメリット
①メリット
・長期保証
多くの大手ハウスメーカーは長期保証を設定しています。 条件として、決められた期間ごとにメンテナンス費用を払う必要がありますが、同じ会社に点検してもらえる安心感があります。また、大規模災害が起こった際でも全国に対応窓口があるため、より早く対応してもらえます。
・施工管理
住宅の品質を守るには工事の施工管理も重要です。 工務店は少人数の会社も多く施工と管理が明確に分かれていない場合もあるので、 ハウスメーカーのほうがチェック体制が厳しいと言えます。
・工期が短い
大手ハウスメーカーでは商品がパッケージ化されていて、 規格化された建築材を自社工場であらかじめ製造している場合も多いので、工期が短くなります。
②デメリット
・価格が高い
さまざまなコストが上乗せされているため、ハウスメーカーは工務店より価格が高い傾向があります。
・似たような建物になってしまう
賃貸併用住宅は賃貸ビジネスです。似たような物件が増えてしまうと差別化できなくなり、 物件の価値が築年数と広さによって決まってしまいます。 そうなると、築年数が経つにつれて家賃が下がってしまうため賃貸経営のメリットが少なくなってしまいます。
工務店で建てるメリットとデメリット
①メリット
・価格が抑えられる
工務店の場合は経費が少なく、ハウスメーカーよりも価格を抑えられる場合が多いといえます。
・地域密着で親身になってくれる
工務店は地域に密着したサービスを行っています。何かあったときには、スピーディかつ柔軟に対応してもらえるでしょう。建築後のリフォームや増築といった相談もしやすくなります。
②デメリット
・大工の当たりはずれがある
工務店の場合、大工の腕や担当者の知識によって仕上がりにムラが出やすい点は否めません。施工に優れた建材やデザインを優先させることが多いので、好みのデザインに仕上げてくれる優れた工務店を探す努力が必要になります。
・大手と比べると保証が充実していない
災害対応という点や、20年などの長期にわたる保証がない点は、工務店のデメリットといえます。
しかし、ハウスメーカーでも工務店でも保証がない会社はありません。 法律によって新築住宅には「10年間の瑕疵担保責任」が決められており、 購入時に分からなかった欠陥が見つかっても10年間は住宅メーカーが保証してくれます。 たとえ工務店が倒産しても、10年間の保証が引き継がれることが法律で決められているので心配はいりません。
・賃貸経営の知識がない
賃貸併用住宅は、自宅でありながら賃貸部分から家賃収入を得られるビジネスでもあります。 地元の工務店は賃貸経営の実績が少ない会社が多く、賃貸併用住宅を建ててもその後の賃貸経営のサポートが受けられない可能性が高いといえます。 家賃収入を継続的に得て豊かな暮らしを送るためにも入居者を決めるノウハウがある会社を選ぶ必要があります。
賃貸併用住宅のメーカー選びで気をつけること
・担当者が信頼できる
工務店でもハウスメーカーでも、外せないのは「担当者が良い」「会社が信頼できる」という人間関係や会社に対する安心感です。
・価格
賃貸併用住宅で成功する上で収支に関わる非常に重要なポイントになるのが価格です。値段以上の価値があるかを考え、ハウスメーカーや工務店をしっかり比較検討してください。
・賃貸の実績
特にはじめて賃貸経営をされる方に欠かせない条件が、賃貸物件の実績があるかどうか。賃貸経営の運営サポート体制が確立されている会社を選びましょう。
普段、会社勤めをしている方にとって「入居募集・ポータルサイトでの告知・賃貸借契約・家賃管理・苦情対応etc.」を自分で行なうというのは、非現実的だと思います。既に、アパート経営をしていて、それが本業であれば十分可能ですが、知識も経験もないなかでは難しいですよね。
建築会社を選ぶにあたっては、賃貸経営の運営サポート体制が確立されているかも大きなポイントといえるでしょう。
バンクスホームはここが違う
株式会社GIFTでは、マイホーム+賃貸を住宅ローンで建てる、新しい賃貸併用住宅「BANK’S HOME(バンクスホーム)」をご提案しています。ここでは、バンクスホームについて、ハウスメーカーと工務店と比較をしながらご紹介させていただきます。
①価格がハウスメーカーより安い
ハウスメーカーの場合、粗利は建築費用の40~50%といわれていますが、私たちバンクスホームはその半分で利益設定しています。
②賃貸経営の実績がある
価格だけで言えば、工務店との差はありません。
ただし、工務店には賃貸経営の実績はありませんが、私たち株式会社GIFTは女性専用アパートメントPRIMAで10年以上の経験があり、全国2600戸、平均入居率97.4%の実績があります。
仮に同じ価格だとしても、その後の賃貸経営が成功するかどうかは建築会社のノウハウやサポートにかかっています。どのような物件が入居者に好まれるか、年月を経ても家賃を下げない物件のノウハウは、長く住んでもらうための工夫の積み重ねをしてきた弊社だからこそ提供できるサービスです。
また、工務店は普段注文住宅を多く建てています。 賃貸物件を建てる際に「アパートだから」という気持ちで賃貸部分の設備の質を下げるコストカットをすることがありますが、賃貸経営においては非常に危険です。
収益性の高さだけを考えて安く建てると、物件は周りに埋もれてしまいます。似たような物件が多くあるので、少しでも好条件の部屋を見つけると入居者は引っ越してしまうのです。質の良い建物で差別化をすることが、安定した賃貸経営につながります。
この記事のまとめ
- ハウスメーカーと工務店では賃貸併用住宅を建てると800万円以上の価格差がある。
- ハウスメーカーは価格が高めだが、長期保証の安心感がある。
- 工務店は価格は安いが、賃貸のノウハウがないので賃貸併用住宅には向いていない。
- 賃貸併用住宅では「価格」と「賃貸の経験」に気をつけて建築会社を選ぶと良い。
- バンクスホームは工務店並みの価格で、賃貸経営サポートまで受けられる。
バンクスホームでは、「将来のお金に対する不安」を解決してくれる賃貸併用住宅について、下記の記事でより詳しくお伝えしていますので、ぜひ併せてチェックしてみてください!
関連記事:賃貸併用住宅〜メリット・デメリットと後悔しない家づくり
「バンクスホーム」は賃貸併用住宅を住宅ローンで建てる、今までにはなかった新築住宅。詳しくは下記のオフィシャルサイトでご案内していますので、ぜひこちらからご参照ください。
バンクスホーム オフィシャルサイト